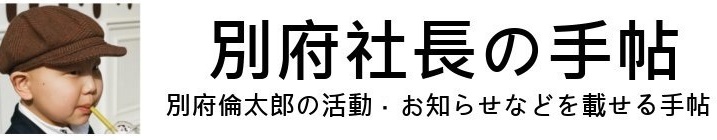

別府社長の手帖23
「石とぼく」
文章 別府倫太郎 2015年3月27日更新
今、目の前には美しく黒光りした湯呑茶碗がある。
しゅっとした外見は、見とれてしまうほどで
それでいながら、その湯呑茶碗には、
どこか「含み」がある。
手に持ってみても、とても持ちやすく飲みやすい。
特に、瀬戸物に詳しくないぼくでも、
ずっと見てしまうのだ。
この湯呑茶碗はよく行く瀬戸物屋さんで、
買ったんだけれど、どこか力があるな、とほんとうに思う。
もう前から気になっていたものなのだけれど、
こうあらためて見ていると、本当に嬉しいような
気もちがこみあげてくるのだ。
しかし、こういう瀬戸物でも、古い骨董品でも、
なんでもいいのだけれど「もの」というのは、
「もの」の力を持っている、ということに最近、
ぼくは気が付いている。
この湯呑にしても、日々の不安とか心配とかそういう
「小さい揺れ」みたいなものを整理してくれるし、
本当に「いいもの」とか古いものを
見ているだけでも、気持ちはすっきりとする。
その力がなんなのかはぼくもよくわからないのだけれど、
強くそういう力を感じるのだ。
だから、ぼくは瀬戸物屋に行ったりするのが好きなのだろう。
といっても、たまに行ける時だけ行くのだけれど、
ぼくにはもっとそういう力を求める気持ちが強かった時がある。
その時は、その求める気持ちに気づかないほどに
そのことを求めていた。
その時にしたこと、それはどんなことか。
今と同じように瀬戸物を鑑賞していたわけではない。
その奥にある一つのものを探していたのである。
「もの」ということを直接的に伝えるもの。
それはぼくにとって「石」だったのである。
何もかも、垣根を持たない、そこらへんに落ちているような石。
それらが一つ一つ何かを語っているように、
当時のぼくは思っていたのである。
いや、それともその石が語っていることを
読み取ろうとしていたのかもしれない。
どっちにしろ、ぼくは何の理由もなしにそのことを
必要としていたのである。
本当に最初は日々の小さなことだったのだが、
それが大きな影響を及ぼすような、そんな感じ。
道端に落ちていた小さな石ころを持ち帰るのが好きで、
それがこうじて近くに流れている信濃川に降りて、
石を拾って持ち帰ったりもしていた。
さらには、持ち帰れないような大きな石には
名前をつけたりもしていたことをよく覚えている。
はたから見れば怪しさ満点なのだろうが、
その時は「石」に触れること、それが本当に楽しかったのだ。
そのことに理由もなく、何も語らないけれど、
その姿が力をもっているようなそんな「石」にできるだけ
触れていたかった。
母もそれに付き合ってくれたりして、二人でよく
自転車で行ったりしていたのだ。
その時は、学校に行けなくなった初めの頃で
「本当に行かなくていいんだろうか・・・
自分は何をしているんだろうか・・・」
と不安になりがら自分を見つめていた時期だったから
特に不安をじっと見つめてくれる「もの」の力が必要だったんだろう。
今はその「行為」というのはしていないが、
瀬戸物屋に行ったり「もの」と触れる時には
やっぱり「ふっ」と思い出して考えたりすることもある。
だから、その「石」と向き合った時間は善い悪いではなく
自分にとって「考える」プロセスの
一つだったんだな、とふと思う。
ぼくの中には、その心というのがいつまでも残っていて、
それが自分自身の成分になっているような
そんな感じのことがきっとあるのだ。
その「証」としての石なのである。
だから、いつまでもそのプロセスというのを大切にしたいし、
当たり前のことに踏みとどまれるようなそんな力を持っていきたい。
「触れる」ということを軸にものと
向き合えたらいいな、と思うのだ。
それはきっと本当に善いも悪いもない
「たいせつなこと」なのである。
今、目の前には美しく黒光りした湯呑茶碗がある。
しゅっとした外見は、見とれてしまうほどで
それでいながら、その湯呑茶碗には、
どこか「含み」がある。
手に持ってみても、とても持ちやすく飲みやすい。
特に、瀬戸物に詳しくないぼくでも、
ずっと見てしまうのだ。
この湯呑茶碗はよく行く瀬戸物屋さんで、
買ったんだけれど、どこか力があるな、とほんとうに思う。
もう前から気になっていたものなのだけれど、
こうあらためて見ていると、本当に嬉しいような
気もちがこみあげてくるのだ。
しかし、こういう瀬戸物でも、古い骨董品でも、
なんでもいいのだけれど「もの」というのは、
「もの」の力を持っている、ということに最近、
ぼくは気が付いている。
この湯呑にしても、日々の不安とか心配とかそういう
「小さい揺れ」みたいなものを整理してくれるし、
本当に「いいもの」とか古いものを
見ているだけでも、気持ちはすっきりとする。
その力がなんなのかはぼくもよくわからないのだけれど、
強くそういう力を感じるのだ。
だから、ぼくは瀬戸物屋に行ったりするのが好きなのだろう。
といっても、たまに行ける時だけ行くのだけれど、
ぼくにはもっとそういう力を求める気持ちが強かった時がある。
その時は、その求める気持ちに気づかないほどに
そのことを求めていた。
その時にしたこと、それはどんなことか。
今と同じように瀬戸物を鑑賞していたわけではない。
その奥にある一つのものを探していたのである。
「もの」ということを直接的に伝えるもの。
それはぼくにとって「石」だったのである。
何もかも、垣根を持たない、そこらへんに落ちているような石。
それらが一つ一つ何かを語っているように、
当時のぼくは思っていたのである。
いや、それともその石が語っていることを
読み取ろうとしていたのかもしれない。
どっちにしろ、ぼくは何の理由もなしにそのことを
必要としていたのである。
本当に最初は日々の小さなことだったのだが、
それが大きな影響を及ぼすような、そんな感じ。
道端に落ちていた小さな石ころを持ち帰るのが好きで、
それがこうじて近くに流れている信濃川に降りて、
石を拾って持ち帰ったりもしていた。
さらには、持ち帰れないような大きな石には
名前をつけたりもしていたことをよく覚えている。
はたから見れば怪しさ満点なのだろうが、
その時は「石」に触れること、それが本当に楽しかったのだ。
そのことに理由もなく、何も語らないけれど、
その姿が力をもっているようなそんな「石」にできるだけ
触れていたかった。
母もそれに付き合ってくれたりして、二人でよく
自転車で行ったりしていたのだ。
その時は、学校に行けなくなった初めの頃で
「本当に行かなくていいんだろうか・・・
自分は何をしているんだろうか・・・」
と不安になりがら自分を見つめていた時期だったから
特に不安をじっと見つめてくれる「もの」の力が必要だったんだろう。
今はその「行為」というのはしていないが、
瀬戸物屋に行ったり「もの」と触れる時には
やっぱり「ふっ」と思い出して考えたりすることもある。
だから、その「石」と向き合った時間は善い悪いではなく
自分にとって「考える」プロセスの
一つだったんだな、とふと思う。
ぼくの中には、その心というのがいつまでも残っていて、
それが自分自身の成分になっているような
そんな感じのことがきっとあるのだ。
その「証」としての石なのである。
だから、いつまでもそのプロセスというのを大切にしたいし、
当たり前のことに踏みとどまれるようなそんな力を持っていきたい。
「触れる」ということを軸にものと
向き合えたらいいな、と思うのだ。
それはきっと本当に善いも悪いもない
「たいせつなこと」なのである。
(第23回「石とぼく」終わり)
別府社長の手帖いままでのタイトル
第1回「そこに居る光」2013-7-21更新
第2回「今を得るだけでは得られないもの」2013-7-28更新
第3回「生きるって何?死って何?病気とは何?」2013-8-7更新
第4回「見えないところに本質がある」2013-9-22更新
第5回「ボーっとすること」2014-9-22更新
第6回「カメラのこと」2014-5-31更新
第7回「ペロペロ、ソフトクリーム」2014-5-31更新
第8回「みそ汁、するする」2014-6-16更新
第9回「限界とぼく」2014-7-5更新
第10回「息子のまなざし」2014-7-13更新
第11回「分からないことの存在」2014-9-17更新
第12回「聞くと書く」2014-9-19更新
第13回「いじめという意見」2014-9-19更新
第14回「小さな火のなかで」2014-9-30更新
第15回「一番目の事実」2014-10-2更新
第16回「毎週金曜日」2015-1-30更新
第17回「ひきこもり計画」2015-2-6更新
第18回「寒ブリと焼き芋」2015-2-13更新
第19回「倫太郎のゆめ」2015-2-20更新
第20回「原稿一枚分の詩」2015-2-27更新
第21回「ライフ・イズ・ビューティフル」2015-3-6更新
第22回「体の反応」2015-3-20更新
第23回「石とぼく」2015-3-27更新
第24回「蚊に刺されて」2015-6-2更新
第25回「最後に」2015-8-9更新
別府新聞ホームへ戻る
別府社長の手帖いままでのタイトル
第1回「そこに居る光」2013-7-21更新
第2回「今を得るだけでは得られないもの」2013-7-28更新
第3回「生きるって何?死って何?病気とは何?」2013-8-7更新
第4回「見えないところに本質がある」2013-9-22更新
第5回「ボーっとすること」2014-9-22更新
第6回「カメラのこと」2014-5-31更新
第7回「ペロペロ、ソフトクリーム」2014-5-31更新
第8回「みそ汁、するする」2014-6-16更新
第9回「限界とぼく」2014-7-5更新
第10回「息子のまなざし」2014-7-13更新
第11回「分からないことの存在」2014-9-17更新
第12回「聞くと書く」2014-9-19更新
第13回「いじめという意見」2014-9-19更新
第14回「小さな火のなかで」2014-9-30更新
第15回「一番目の事実」2014-10-2更新
第16回「毎週金曜日」2015-1-30更新
第17回「ひきこもり計画」2015-2-6更新
第18回「寒ブリと焼き芋」2015-2-13更新
第19回「倫太郎のゆめ」2015-2-20更新
第20回「原稿一枚分の詩」2015-2-27更新
第21回「ライフ・イズ・ビューティフル」2015-3-6更新
第22回「体の反応」2015-3-20更新
第23回「石とぼく」2015-3-27更新
第24回「蚊に刺されて」2015-6-2更新
第25回「最後に」2015-8-9更新
別府新聞ホームへ戻る