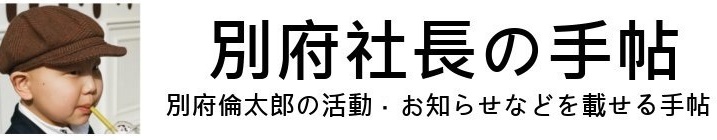

別府社長の手帖12
「わからないことの存在」
文章 別府倫太郎 2014年9月17日更新
「わからないこと」というのがある。
それは、どこかに存在する。
たとえば、山に行ったとすれば、名前もわからない、
なにをしているのかもわからない虫がいたり
どういう実がなるのかわからない木もある。
そして、土や地中、山おく、みんなわからない。
そもそも「しぜん」もわからない。
< 「わからないことを知らないことよりも
わからないことを知っていることの方が、すこし賢い」
ということを聞いたり、自分でも書いたりして考えたのだが
この言葉には、何か「なるほど」と思わせる感じがあるようだ。
それは、煮詰めれば、煮詰めるほど、味が薄まるような気がするし
なにか、どうしようもない気がする。
それと話がつながるかどうか、わからないが
こんな話しを聞いたことがある。
「山奥の電気もとおっていないところに
外国人が住んでいて、自給自足の生活をしているみたいよ。
それで、ちかくに新幹線が通っちゃって新幹線がときどき見えちゃう。
それが見えるのがイヤで別のところに移り住んだみたいよ。すごいね。」
というはなし。
この話しを聞いたとき、僕は、まるで
わからないことを知っているようにしているみたいだと
思ったのだ。そう思ったのは、ぼくだけだろうか。
まぁ、とにかく、これは、ただ逃げているだけなんじゃないだろうか。
「にげる」というのは、ライオンとうさぎが
出会ってしまったとき、うさぎが「にげる」ことの「にげる」ではない。
そして、ぼくは学校に行っていないのだが、
よく僕は「学校からにげた」とよく言う。
だが、その「にげる」でもない。
げんに僕は、いろいろ学校のことについても思っている。
それは遠くのどこかで聞いてくれることを願っているからだ。
そうなると思っているからだ。
だから、ちがう。
じゃあ、その「にげる」とは何か?
それは自分、わからないことから「にげる」ということだ。
もし、その人が新幹線がイヤだと思ったなら、
その新幹線がある世界に居る自分も新幹線なんだと思うほかない。
そうでなければ、それはただの自己満足だ。
そして、さっき、ぼくは
「わからないことを知っているようだ」と言ったが、
しれはわからないことを認めてないということになる。
僕が思うに、わからないことはある。
そのことはやっぱり、わからないから怖い。
けれど、否定はできない。
つまり、そこにあるということだ。
そして、僕はそのわからないことのなかでしか
活きれない、生きざるをえないのだと思う。
それがわからないことを知っているのではなく、感じていること。
ほかの人がどうかはわからないが、ぼくはそうせざるをえない。
ぼくはそう思う。
わからないことの中でそう思う。
作者
別府倫太郎 プロフィール

2002年12月5日生まれ。
新潟県十日町市在住。
3年前から始めた「別府新聞」の社長でもあり、
別府新聞のたった一人の社員でもある。
「学校に行っていない思想家」「ポレポレぼうや」など
色々な呼び名がある。
「わからないこと」というのがある。
それは、どこかに存在する。
たとえば、山に行ったとすれば、名前もわからない、
なにをしているのかもわからない虫がいたり
どういう実がなるのかわからない木もある。
そして、土や地中、山おく、みんなわからない。
そもそも「しぜん」もわからない。
< 「わからないことを知らないことよりも
わからないことを知っていることの方が、すこし賢い」
ということを聞いたり、自分でも書いたりして考えたのだが
この言葉には、何か「なるほど」と思わせる感じがあるようだ。
それは、煮詰めれば、煮詰めるほど、味が薄まるような気がするし
なにか、どうしようもない気がする。
それと話がつながるかどうか、わからないが
こんな話しを聞いたことがある。
「山奥の電気もとおっていないところに
外国人が住んでいて、自給自足の生活をしているみたいよ。
それで、ちかくに新幹線が通っちゃって新幹線がときどき見えちゃう。
それが見えるのがイヤで別のところに移り住んだみたいよ。すごいね。」
というはなし。
この話しを聞いたとき、僕は、まるで
わからないことを知っているようにしているみたいだと
思ったのだ。そう思ったのは、ぼくだけだろうか。
まぁ、とにかく、これは、ただ逃げているだけなんじゃないだろうか。
「にげる」というのは、ライオンとうさぎが
出会ってしまったとき、うさぎが「にげる」ことの「にげる」ではない。
そして、ぼくは学校に行っていないのだが、
よく僕は「学校からにげた」とよく言う。
だが、その「にげる」でもない。
げんに僕は、いろいろ学校のことについても思っている。
それは遠くのどこかで聞いてくれることを願っているからだ。
そうなると思っているからだ。
だから、ちがう。
じゃあ、その「にげる」とは何か?
それは自分、わからないことから「にげる」ということだ。
もし、その人が新幹線がイヤだと思ったなら、
その新幹線がある世界に居る自分も新幹線なんだと思うほかない。
そうでなければ、それはただの自己満足だ。
そして、さっき、ぼくは
「わからないことを知っているようだ」と言ったが、
しれはわからないことを認めてないということになる。
僕が思うに、わからないことはある。
そのことはやっぱり、わからないから怖い。
けれど、否定はできない。
つまり、そこにあるということだ。
そして、僕はそのわからないことのなかでしか
活きれない、生きざるをえないのだと思う。
それがわからないことを知っているのではなく、感じていること。
ほかの人がどうかはわからないが、ぼくはそうせざるをえない。
ぼくはそう思う。
わからないことの中でそう思う。
作者
別府倫太郎 プロフィール

2002年12月5日生まれ。
新潟県十日町市在住。
3年前から始めた「別府新聞」の社長でもあり、
別府新聞のたった一人の社員でもある。
「学校に行っていない思想家」「ポレポレぼうや」など
色々な呼び名がある。
(第11回「息子のまなざし」終わり)
別府社長の手帖いままでのタイトル
第1回「そこに居る光」2013-7-21更新
第2回「今を得るだけでは得られないもの」2013-7-28更新
第3回「生きるって何?死って何?病気とは何?」2013-8-7更新
第4回「見えないところに本質がある」2013-9-22更新
第5回「ボーっとすること」2014-9-22更新
第6回「カメラのこと」2014-5-31更新
第7回「ペロペロ、ソフトクリーム」2014-5-31更新
第8回「みそ汁、するする」2014-6-16更新
第9回「限界とぼく」2014-7-5更新
第10回「息子のまなざし」2014-7-13更新
第11回「分からないことの存在」2014-9-17更新
第12回「聞くと書く」2014-9-19更新
第13回「いじめという意見」2014-9-19更新
第14回「小さな火のなかで」2014-9-30更新
第15回「一番目の事実」2014-10-2更新
第16回「毎週金曜日」2015-1-30更新
第17回「ひきこもり計画」2015-2-6更新
第18回「寒ブリと焼き芋」2015-2-13更新
第19回「倫太郎のゆめ」2015-2-20更新
第20回「原稿一枚分の詩」2015-2-27更新
第21回「ライフ・イズ・ビューティフル」2015-3-6更新
第22回「体の反応」2015-3-20更新
第23回「石とぼく」2015-3-27更新
第24回「蚊に刺されて」2015-6-2更新
第25回「最後に」2015-8-9更新
別府新聞ホームへ戻る
別府社長の手帖いままでのタイトル
第1回「そこに居る光」2013-7-21更新
第2回「今を得るだけでは得られないもの」2013-7-28更新
第3回「生きるって何?死って何?病気とは何?」2013-8-7更新
第4回「見えないところに本質がある」2013-9-22更新
第5回「ボーっとすること」2014-9-22更新
第6回「カメラのこと」2014-5-31更新
第7回「ペロペロ、ソフトクリーム」2014-5-31更新
第8回「みそ汁、するする」2014-6-16更新
第9回「限界とぼく」2014-7-5更新
第10回「息子のまなざし」2014-7-13更新
第11回「分からないことの存在」2014-9-17更新
第12回「聞くと書く」2014-9-19更新
第13回「いじめという意見」2014-9-19更新
第14回「小さな火のなかで」2014-9-30更新
第15回「一番目の事実」2014-10-2更新
第16回「毎週金曜日」2015-1-30更新
第17回「ひきこもり計画」2015-2-6更新
第18回「寒ブリと焼き芋」2015-2-13更新
第19回「倫太郎のゆめ」2015-2-20更新
第20回「原稿一枚分の詩」2015-2-27更新
第21回「ライフ・イズ・ビューティフル」2015-3-6更新
第22回「体の反応」2015-3-20更新
第23回「石とぼく」2015-3-27更新
第24回「蚊に刺されて」2015-6-2更新
第25回「最後に」2015-8-9更新
別府新聞ホームへ戻る