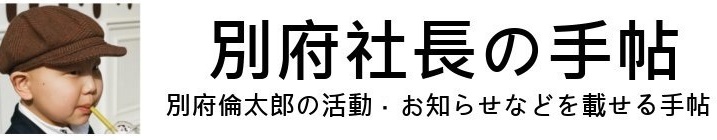

別府社長の手帖14
「小さな火のなかで」
文章 別府倫太郎 2014年9月30日更新
きのうの真夜中、ぼくは「すべての怒りは水のごとくに」
という本に出会っていた。
ちなみに、ぼくの名前、「倫太郎」は、この本を書いた
灰谷健次郎の「天の瞳」の主人公、倫太郎からとったもの。
その灰谷さんが書いた「すべての怒りは水のごとくに」は、
ある少女の手紙からはじまる。
その手紙は、学校への疑問と大切なことについて、
たんたんに書かれている。
学校にいると、大切なこと、考える時間が無いような気する。
そんな感じのことが書いていあるのだ。
それで、書いている少女は、新潟出身で、
不登校児であるところは、ぼくと同じ。
しかし、本当に痛くなるほどすごい、その手紙は
ぼくたちが学校に行かないことでのこせた、
真理への感覚と想像力を小さな火へとみちびく。
その火は、「消える」ことが許されない火だ。
学校をいちばん、思っているからこそのものだ。
そして、ぼくにとって、その火は、「つみ」に
見えてくるときもある。
でも、マイナスとか、プラスとか、そういう意味ではない。
「そこにあるもの」なのだ。
今の「生きている」ことをつかむための「つみ」であり、力である。
自分が差別をしている、という意識があるからこそ、
そこに世界の真理が見える。
「つみ」=小さな火は、そういうものなのです。
しかし、それでいても人々は、その火を消そうとする。
こくこくと変わり続ける火のなかにある、
継続する意思におそれているのであろう。
学校をふくむ、ヘンな意味での、「組織」は
しらずしらずのうちに、のがれようとするのだ。
だけど、やはり、どうしても、のがれなれない
「小さな火」がある。「つみ」がある。
人は、どこかで、差別をする。
ぼくは、それをたやさず、うける。
ぼくも、たやさず、してしまう。
だから、僕たちは「いじめられる側」にたつことは
ぜったいにできない。このことは、本当だ。
もし、「いじめられる側」にたてるなら、
たってみたいものだが、そうなったら、今の自分はいないだろう。
でも、ここで注意してほしい。
それは、「いじめ」というのは、50%ずつ悪いなんてことはないということ。
「いじめ」という本来の意味で言うと、どっちかが100%悪いのだ。
まぁ、さっき、言ってていることと矛盾しているかもしれないが
つまり、ぼくが言いたいのは、
人には、それぞれ「小さな火」があり、
それは、「つみ」から生まれるものである。
その「つみ」は、さっき「いじめ」のことで言った
100%のものから生まれ、
その力は、人間が生きるなかで、必要である。
ということ。
しかし、この少女の手紙から、感じたものが、もう一つある。
それは、学校の人たちや、学校を「いい」と思っている人たちの目線だ。
その人たちは、まるで、生きることをやめさせるかのように「小さな火」を消す。
まるで、「いじめられている側」です、と言っているように「つみ」をもみ消す。
ぼくは、この人たちが、なにを見ているか、
「生きる」ことをつかんでいるか、
わからないから本当に怖いな、と思う。
なぜ、そうなったかは、わからないが、
学校にいるうちに、しらずしらずのうちに
人間のうらにある、迷って、うろうろそている思いが
一つの「組織」となり、そうなったのであろう。
しかし、そこには、「調和」というものがない。
「意見」だけがあるのだ。
そして、それは、ぼくやぼくの母や、
手紙を書いた少女たちを除いて、
ほとんどの全国民は、「意見」をもっているのではないだろうか。
それで、「意見」というのは、
(意見のことは、前回の「いじめという意見」で詳しく書きました)
つまり、さきほどの「組織」みたいなこと。
すこしの恐れと、すこしの自分への偽りをふくんだ、
うらの思い。
「学校には行った方がいい」
「学校に行かないと、賢くならない」
「やはり、「学校」という名の基礎を学んだほうがいい」
「同年代と遊ばなくちゃならない。
今しか、できないことをしなければならない」
などなど。色々とあるのです。
でも、本人に聞くと、もちろん
「そんな、つもりはない」と言うのですが、
おでこにそう書いてあるし、「学校に行かないほうがいい」という
人は、ほとんど、いないと思います。
しかし、それとはぎゃくに、1人、学校に行かない事を
肯定してくれる人がいたのです。
その人とは、灰谷健次郎さん。
この「すべての怒りは水のごとくに」のなかで、
「わたしは少女の言い分をまるごと肯定する立場をとる」
と書いてあるのです。
これは、すごいことを言っているんじゃないでしょうか。
それでいて、この言葉には「肯定」というだけでなく、
「小さな火」があり、「つみ」があるのです。
本当に本当にすばらしい人だと思います。
ぼくは、この本に出会えてよかった。
そして、ぼくは「つみ」について、
これからも、考え続けなければいけないと思ったのです。
それは、人のために簡単になれない、
ほとんどならないものですが、
こころを、たましいを、つよく、たたくことはできるのではないでしょうか。
タイトルの「すべての怒りは水のごとくに」のように、
しずかな力をため、「小さな火」で、生きるということを
つよく感じていきたいと思った、「天の瞳」の倫太郎でした。
作者
別府倫太郎 プロフィール

2002年12月5日生まれ。
新潟県十日町市在住。
3年前から始めた「別府新聞」の社長でもあり、
別府新聞のたった一人の社員でもある。
「学校に行っていない思想家」「ポレポレぼうや」など
色々な呼び名がある。
きのうの真夜中、ぼくは「すべての怒りは水のごとくに」
という本に出会っていた。
ちなみに、ぼくの名前、「倫太郎」は、この本を書いた
灰谷健次郎の「天の瞳」の主人公、倫太郎からとったもの。
その灰谷さんが書いた「すべての怒りは水のごとくに」は、
ある少女の手紙からはじまる。
その手紙は、学校への疑問と大切なことについて、
たんたんに書かれている。
学校にいると、大切なこと、考える時間が無いような気する。
そんな感じのことが書いていあるのだ。
それで、書いている少女は、新潟出身で、
不登校児であるところは、ぼくと同じ。
しかし、本当に痛くなるほどすごい、その手紙は
ぼくたちが学校に行かないことでのこせた、
真理への感覚と想像力を小さな火へとみちびく。
その火は、「消える」ことが許されない火だ。
学校をいちばん、思っているからこそのものだ。
そして、ぼくにとって、その火は、「つみ」に
見えてくるときもある。
でも、マイナスとか、プラスとか、そういう意味ではない。
「そこにあるもの」なのだ。
今の「生きている」ことをつかむための「つみ」であり、力である。
自分が差別をしている、という意識があるからこそ、
そこに世界の真理が見える。
「つみ」=小さな火は、そういうものなのです。
しかし、それでいても人々は、その火を消そうとする。
こくこくと変わり続ける火のなかにある、
継続する意思におそれているのであろう。
学校をふくむ、ヘンな意味での、「組織」は
しらずしらずのうちに、のがれようとするのだ。
だけど、やはり、どうしても、のがれなれない
「小さな火」がある。「つみ」がある。
人は、どこかで、差別をする。
ぼくは、それをたやさず、うける。
ぼくも、たやさず、してしまう。
だから、僕たちは「いじめられる側」にたつことは
ぜったいにできない。このことは、本当だ。
もし、「いじめられる側」にたてるなら、
たってみたいものだが、そうなったら、今の自分はいないだろう。
でも、ここで注意してほしい。
それは、「いじめ」というのは、50%ずつ悪いなんてことはないということ。
「いじめ」という本来の意味で言うと、どっちかが100%悪いのだ。
まぁ、さっき、言ってていることと矛盾しているかもしれないが
つまり、ぼくが言いたいのは、
人には、それぞれ「小さな火」があり、
それは、「つみ」から生まれるものである。
その「つみ」は、さっき「いじめ」のことで言った
100%のものから生まれ、
その力は、人間が生きるなかで、必要である。
ということ。
しかし、この少女の手紙から、感じたものが、もう一つある。
それは、学校の人たちや、学校を「いい」と思っている人たちの目線だ。
その人たちは、まるで、生きることをやめさせるかのように「小さな火」を消す。
まるで、「いじめられている側」です、と言っているように「つみ」をもみ消す。
ぼくは、この人たちが、なにを見ているか、
「生きる」ことをつかんでいるか、
わからないから本当に怖いな、と思う。
なぜ、そうなったかは、わからないが、
学校にいるうちに、しらずしらずのうちに
人間のうらにある、迷って、うろうろそている思いが
一つの「組織」となり、そうなったのであろう。
しかし、そこには、「調和」というものがない。
「意見」だけがあるのだ。
そして、それは、ぼくやぼくの母や、
手紙を書いた少女たちを除いて、
ほとんどの全国民は、「意見」をもっているのではないだろうか。
それで、「意見」というのは、
(意見のことは、前回の「いじめという意見」で詳しく書きました)
つまり、さきほどの「組織」みたいなこと。
すこしの恐れと、すこしの自分への偽りをふくんだ、
うらの思い。
「学校には行った方がいい」
「学校に行かないと、賢くならない」
「やはり、「学校」という名の基礎を学んだほうがいい」
「同年代と遊ばなくちゃならない。
今しか、できないことをしなければならない」
などなど。色々とあるのです。
でも、本人に聞くと、もちろん
「そんな、つもりはない」と言うのですが、
おでこにそう書いてあるし、「学校に行かないほうがいい」という
人は、ほとんど、いないと思います。
しかし、それとはぎゃくに、1人、学校に行かない事を
肯定してくれる人がいたのです。
その人とは、灰谷健次郎さん。
この「すべての怒りは水のごとくに」のなかで、
「わたしは少女の言い分をまるごと肯定する立場をとる」
と書いてあるのです。
これは、すごいことを言っているんじゃないでしょうか。
それでいて、この言葉には「肯定」というだけでなく、
「小さな火」があり、「つみ」があるのです。
本当に本当にすばらしい人だと思います。
ぼくは、この本に出会えてよかった。
そして、ぼくは「つみ」について、
これからも、考え続けなければいけないと思ったのです。
それは、人のために簡単になれない、
ほとんどならないものですが、
こころを、たましいを、つよく、たたくことはできるのではないでしょうか。
タイトルの「すべての怒りは水のごとくに」のように、
しずかな力をため、「小さな火」で、生きるということを
つよく感じていきたいと思った、「天の瞳」の倫太郎でした。
作者
別府倫太郎 プロフィール

2002年12月5日生まれ。
新潟県十日町市在住。
3年前から始めた「別府新聞」の社長でもあり、
別府新聞のたった一人の社員でもある。
「学校に行っていない思想家」「ポレポレぼうや」など
色々な呼び名がある。
(第14回「小さな火のなかで」終わり)
別府社長の手帖いままでのタイトル
第1回「そこに居る光」2013-7-21更新
第2回「今を得るだけでは得られないもの」2013-7-28更新
第3回「生きるって何?死って何?病気とは何?」2013-8-7更新
第4回「見えないところに本質がある」2013-9-22更新
第5回「ボーっとすること」2014-9-22更新
第6回「カメラのこと」2014-5-31更新
第7回「ペロペロ、ソフトクリーム」2014-5-31更新
第8回「みそ汁、するする」2014-6-16更新
第9回「限界とぼく」2014-7-5更新
第10回「息子のまなざし」2014-7-13更新
第11回「分からないことの存在」2014-9-17更新
第12回「聞くと書く」2014-9-19更新
第13回「いじめという意見」2014-9-19更新
第14回「小さな火のなかで」2014-9-30更新
第15回「一番目の事実」2014-10-2更新
第16回「毎週金曜日」2015-1-30更新
第17回「ひきこもり計画」2015-2-6更新
第18回「寒ブリと焼き芋」2015-2-13更新
第19回「倫太郎のゆめ」2015-2-20更新
第20回「原稿一枚分の詩」2015-2-27更新
第21回「ライフ・イズ・ビューティフル」2015-3-6更新
第22回「体の反応」2015-3-20更新
第23回「石とぼく」2015-3-27更新
第24回「蚊に刺されて」2015-6-2更新
第25回「最後に」2015-8-9更新
別府新聞ホームへ戻る
別府社長の手帖いままでのタイトル
第1回「そこに居る光」2013-7-21更新
第2回「今を得るだけでは得られないもの」2013-7-28更新
第3回「生きるって何?死って何?病気とは何?」2013-8-7更新
第4回「見えないところに本質がある」2013-9-22更新
第5回「ボーっとすること」2014-9-22更新
第6回「カメラのこと」2014-5-31更新
第7回「ペロペロ、ソフトクリーム」2014-5-31更新
第8回「みそ汁、するする」2014-6-16更新
第9回「限界とぼく」2014-7-5更新
第10回「息子のまなざし」2014-7-13更新
第11回「分からないことの存在」2014-9-17更新
第12回「聞くと書く」2014-9-19更新
第13回「いじめという意見」2014-9-19更新
第14回「小さな火のなかで」2014-9-30更新
第15回「一番目の事実」2014-10-2更新
第16回「毎週金曜日」2015-1-30更新
第17回「ひきこもり計画」2015-2-6更新
第18回「寒ブリと焼き芋」2015-2-13更新
第19回「倫太郎のゆめ」2015-2-20更新
第20回「原稿一枚分の詩」2015-2-27更新
第21回「ライフ・イズ・ビューティフル」2015-3-6更新
第22回「体の反応」2015-3-20更新
第23回「石とぼく」2015-3-27更新
第24回「蚊に刺されて」2015-6-2更新
第25回「最後に」2015-8-9更新
別府新聞ホームへ戻る