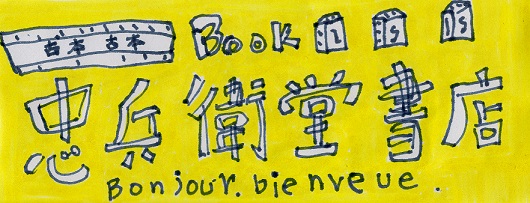
忠兵衛堂書店1
「14歳の君へ」池田晶子さん
今日の本「14歳の君へ」
何のために生きてゆかなければならないのだろうか。
君は、幸福な人生を生きなくちゃならない。
迷っている心に、自ら考える力を――。
毎日中学生新聞の連載から生まれた、さいごの書下ろし作品。
中学生へ向けて平易な言葉で語った人生の教科書。
「受験の役には立ちませんが、人生の役には必ず立ちます」
毎日新聞社 2006年12月刊 ◆定価1200円
(池田晶子ホームページより)
この本は、僕が最初に読んだ池田晶子さんの本。
読んでみると、ちょっと意味は違うけれど
「水をえた魚」のようにごくごくと
「池田晶子成分」がしみこんでいきました。
こういう人のこういう考えは、とても
人間が生き抜くうえに必要なのではないでしょうか。
そのためにも、読んでいただきたい本です。
(池田晶子さんプロフィールは公式ページへ
http://www.nobody.or.jp/ikeda)
文章 別府倫太郎 2014年9月30日更新
池田晶子さんという人が居る。
その人は、「文筆家」と名のったり、
「哲学者」となのったりしている。
その人は、とにかく、自分の中で完結していること
、 つまり「考え」を外に出すことをしていることは、まちがいない。
世の中にある、匿名性があって、責任を隠すこともできる、
「小さないじわる」をこの人は、こまかく、
感じられることの全てを書きだそうとしていることもまちがいない。
そして、その「小さないじわる」というものは、
言うほどでもないのだけれど、
ちょっと道路の白線をはみ出しただけで、
車のクラクションを鳴らされたり、
一つのささいなことだけど、返事がこなかったり
責任を感じさせない一言を言われたり、というようなこと。
その「小さないじわる」が、今、電波のように
飛びかっている。
池田さんは、その飛びかっている電波を
ささいなことを書く人だ。
さきほどと同じように、内内でなぁなぁでおわってしまう、
ひと時の「小さないじわる」を池田さんは、ずっと書く。
池田さんは、しつこい人でもあり、
すべてに責任をもてる人でもあるのだ。
そして、その池田さんが書いた本が今、手元にある。
「14歳の君へ」という本。
ぼくがずっと、もっている本だ。
とても、とても、ていねいに書いてあって、
それは、すべてのことについて、拓かれること。
ここで、そんなことを示すような、一文を紹介したいと思う。
「その後も打ち続く、教育環境の退廃ぶりには、
目を覆う物があります。気の毒なのは、子どもたちです。
せめて、自ら考える力に目覚めることで、不幸な時代を
生き抜く意味に気がつけばと願うものです。
受験の役には、立ちませんが、人生の役には必ず立ちます。
皆様への信頼とともに。
2006年11月 著者」
ここでの「教育環境の廃退ぶり」というのは、さきほど言った
「小さないじわる」のことをさしている。
なぜか? それは学校側の対応、一つにとっても見えてくる。
「そのいじめとは、関係ありません」とか
「事実関係を確認中です」というTVでよく耳にする
「逃げ」の言葉は、「小さないじわる」を、
あることを隠そうとしているし、それでまた
「小さないじわる」が生まれている。そういう状況を
池田さんは言っているのだと思う。
そして
「せめて、自ら考える力に目覚めることで、
不幸な時代を生き抜く意味に気がつけば、と願うものです」
という言葉から、思えるように、
学校をふくむ、社会というもの全体が
「小さないじわる」というものを隠しているからこそ、
子どもも感じとれなくなっている。
だから、せめて、「不幸な時代を生き抜く意味」だけは
感じてほしい。
そして、「人生の役には、必ず立ちます」という
言葉のとおり、それに気づかないと本当の意味での
生きることができないんじゃないだろうか、と思うし、
だからこそ、動力をつかって、池田さんは、内々に終わっている
「小さないじわる」を伝えているのだ、とも思う。
そのことは、体力も使うし、もう身もボロボロになる。
だけど、そうなるしか、生き抜く方法がないのだ。
そして、ちょっと大げさかもしれないけれど、
ぼくたちにとって、生き抜く方法というものは、
この本を読むにほかならないんじゃないだろうか。
それほど、読んでほしい本だし、
読むことで、意味があるのが本なのだし
ぜひとも、読んでいただきたいと今、
池田さんとぼくは固く確信しているのだ。
作者
別府倫太郎 プロフィール

2002年12月5日生まれ。
新潟県十日町市在住。
3年前から始めた「別府新聞」の社長でもあり、
別府新聞のたった一人の社員でもある。
「学校に行っていない思想家」「ポレポレぼうや」など
色々な呼び名がある。
池田晶子さんという人が居る。
その人は、「文筆家」と名のったり、
「哲学者」となのったりしている。
その人は、とにかく、自分の中で完結していること
、 つまり「考え」を外に出すことをしていることは、まちがいない。
世の中にある、匿名性があって、責任を隠すこともできる、
「小さないじわる」をこの人は、こまかく、
感じられることの全てを書きだそうとしていることもまちがいない。
そして、その「小さないじわる」というものは、
言うほどでもないのだけれど、
ちょっと道路の白線をはみ出しただけで、
車のクラクションを鳴らされたり、
一つのささいなことだけど、返事がこなかったり
責任を感じさせない一言を言われたり、というようなこと。
その「小さないじわる」が、今、電波のように
飛びかっている。
池田さんは、その飛びかっている電波を
ささいなことを書く人だ。
さきほどと同じように、内内でなぁなぁでおわってしまう、
ひと時の「小さないじわる」を池田さんは、ずっと書く。
池田さんは、しつこい人でもあり、
すべてに責任をもてる人でもあるのだ。
そして、その池田さんが書いた本が今、手元にある。
「14歳の君へ」という本。
ぼくがずっと、もっている本だ。
とても、とても、ていねいに書いてあって、
それは、すべてのことについて、拓かれること。
ここで、そんなことを示すような、一文を紹介したいと思う。
「その後も打ち続く、教育環境の退廃ぶりには、
目を覆う物があります。気の毒なのは、子どもたちです。
せめて、自ら考える力に目覚めることで、不幸な時代を
生き抜く意味に気がつけばと願うものです。
受験の役には、立ちませんが、人生の役には必ず立ちます。
皆様への信頼とともに。
2006年11月 著者」
ここでの「教育環境の廃退ぶり」というのは、さきほど言った
「小さないじわる」のことをさしている。
なぜか? それは学校側の対応、一つにとっても見えてくる。
「そのいじめとは、関係ありません」とか
「事実関係を確認中です」というTVでよく耳にする
「逃げ」の言葉は、「小さないじわる」を、
あることを隠そうとしているし、それでまた
「小さないじわる」が生まれている。そういう状況を
池田さんは言っているのだと思う。
そして
「せめて、自ら考える力に目覚めることで、
不幸な時代を生き抜く意味に気がつけば、と願うものです」
という言葉から、思えるように、
学校をふくむ、社会というもの全体が
「小さないじわる」というものを隠しているからこそ、
子どもも感じとれなくなっている。
だから、せめて、「不幸な時代を生き抜く意味」だけは
感じてほしい。
そして、「人生の役には、必ず立ちます」という
言葉のとおり、それに気づかないと本当の意味での
生きることができないんじゃないだろうか、と思うし、
だからこそ、動力をつかって、池田さんは、内々に終わっている
「小さないじわる」を伝えているのだ、とも思う。
そのことは、体力も使うし、もう身もボロボロになる。
だけど、そうなるしか、生き抜く方法がないのだ。
そして、ちょっと大げさかもしれないけれど、
ぼくたちにとって、生き抜く方法というものは、
この本を読むにほかならないんじゃないだろうか。
それほど、読んでほしい本だし、
読むことで、意味があるのが本なのだし
ぜひとも、読んでいただきたいと今、
池田さんとぼくは固く確信しているのだ。
作者
別府倫太郎 プロフィール

2002年12月5日生まれ。
新潟県十日町市在住。
3年前から始めた「別府新聞」の社長でもあり、
別府新聞のたった一人の社員でもある。
「学校に行っていない思想家」「ポレポレぼうや」など
色々な呼び名がある。
(第1回「14歳の君へ 池田晶子さん」終わり)
忠兵衛堂書店
第1回「14歳の君へ 池田晶子さん」2014-10-2更新
第2回「バカボン 赤塚不二夫さん」2015-1-26更新
別府新聞ホームへ戻る
忠兵衛堂書店
第1回「14歳の君へ 池田晶子さん」2014-10-2更新
第2回「バカボン 赤塚不二夫さん」2015-1-26更新
別府新聞ホームへ戻る