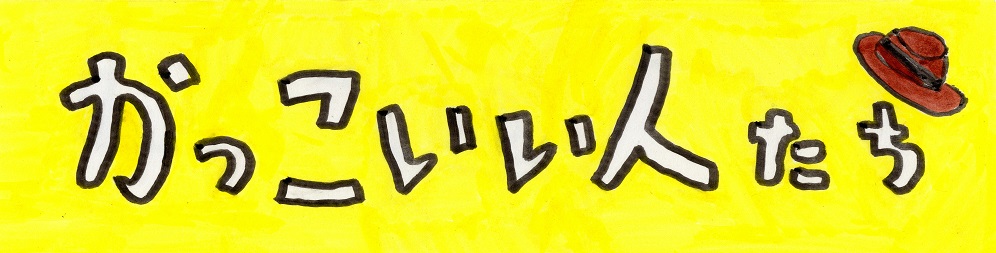
「かっこいい人たち」は、だれにでも「かっこいい」と思われる人じゃない。
ポレポレと話しを聞ける人。(ポレポレはスワヒリ語で「ゆっくり」)
自分の中に「見る」目をもっている人。
「むなしさ」に耳を傾ける人。「魂」を聞ける人。
それが、その人の奥深くにある「かっこいい」ということ。
この「かっこいい人たち」では僕、別府倫太郎(通称ポレポレぼうや)が
「かっこいい人たち」を取材し僕の「目線」でお伝えします。
ポレポレと話しを聞ける人。(ポレポレはスワヒリ語で「ゆっくり」)
自分の中に「見る」目をもっている人。
「むなしさ」に耳を傾ける人。「魂」を聞ける人。
それが、その人の奥深くにある「かっこいい」ということ。
この「かっこいい人たち」では僕、別府倫太郎(通称ポレポレぼうや)が
「かっこいい人たち」を取材し僕の「目線」でお伝えします。
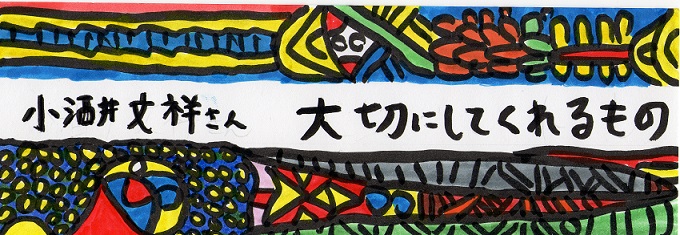

善福寺 僧侶
小酒井文祥さんプロフィール
1945年、新潟県魚沼群津南町に生まれる。
津南町在住。元、学校の国語の先生。(漢詩が専門)
国語の先生として、高校で物理の先生をしていた、かっこいい
人たち第一回の高橋静男さんと同僚となり、今でも大親友。
そして、今は、実家のお寺を継ぎ、お坊さんになっている
プロローグ 「死と対話した人」
文章 別府倫太郎
文祥さんと初めて出会ったのは、かっこいい人たち第一回の
高橋さんからの「新潟県一位のJAZZ好きがいる」という紹介からでした。
行って見たところ、自作のスピーカーや
フランク・シナトラ、ダイアナ・クラールなどの
人たちを紹介してもらい、色々とJAZZ話しを
したんですが、その話をしているとき、
何だか、心地いいなと思いました。
それは、僕も好きなJAZZに囲まれているのもあるのですが、
なんとなく心地いいと思ったのです。
そんなことを思いながら、僕は、文祥さんのお寺、
「善福寺(ぜんぷくじ)」にまた来ていました。
2回目は、かっこいい人たち第4回の岩崎航さんの
「別府倫太郎の締めくくり」にて、
仏教の「関」のことを書きましたが、
そのことについて聞きにきたのです。
そして、いろいろと聞きながら、なるほど、なるほど、と
聞いている中に、やっぱり心地よさがありました。
「関」のことも、もりろんそうなのですが、
その奥に「生死」のことが、ぼくのまなざしには見えてきたんです。
この人は「生死」についての、まなざしがある、と思ったのです。
そして、「まなざし」というのは「問い続けること」ということ。
「知りたい」を超えた何かのことです。
それで、僕は思いました。
「心地よさ」というのは「生死へのまなざし」の
温かみなんじゃないかと思ったんです。
文祥さんの「生死へのまなざし」=「問い続ける」ということが
僕にとって、心地よかった。
そして、そのうえに、ものすごく深い「まなざし」、
つまり、仏教が加わる。
こりゃあ、居心地がいいわけだ、と思いましたね。(笑)
それで、僕はこんな詩を書きました。
「まなざしを持つもの」
「まなざし」というものがある。
道を歩いていると、ある。
僕は、そういう「まなざし」を感じている。
そして、その「まなざし」は、普遍的な「価値」を
僕たちに与えてくれる。
僕は、その「価値」に気づいた時、
自分がなんなのか、わからなくなった。
これは、その「心地よさ」から、生まれた詩だと思っています。
そして、「普遍的な価値」というのは、仏教が言う
「この世のすべてのものが、意味をもち、
一つでもいなければこの世の大きなものが崩れるだろう」
ということからきています。
何もが「価値」をもち「普遍的」だ。
それは、一つの「哲学」とも言えますよね。
そして、その「普遍的な価値」、「哲学」というのが
文祥さんのどこかに存在していると思うのです。
それで、文祥さんと話していくうちに
「死・生・愛・孤独」とか、そういう「根源的」な
ものについて、ずっと問い続けているな、と思いました。
それが、一つの「応え」だと思ったのです。
どういうことかというと、その「問い続けるということ」が
一つの「応え」なんだ、それが一つの「価値」なんだということを
文祥さんから気づかせてもらったんです。
そして、文祥さんは、「死と対話する人」だと思っています。
ぼくは、そこまでは行きませんが、死について考えることが
多いです。そんなとき、「死とは何か」と、
文祥さんに話したくなるんです。
そんなとき、文祥さんは「死」と対話した瞬間のことや
小説からくみ取ったもの、そして、自分の考えまで話してくれます。
「すべて」を話してくれるのです。
こんな、人は初めてですね。
そして、その話してくれるという、その場がもう
「価値」があると思うのです。
それで、さっきの詩の最後は、こう締めくくっています。
「僕は、その「価値」に気づいた時、 自分がなんなのか、わからなくなった」
皆さんは「あれ??」と思うかもしれません。
今まで積み上げていたものはどこ?
「価値」に気づいたら、自分はもっと良くなるんじゃないか?
「矛盾」してないか?と思うはずです。
しかし、そこが「ミソ」なんですよね。(笑)
そもそも、僕が言っている「価値」とは
文祥さんに気づかせてもらった「価値」。
目に見える「価値」ではなく、
何かハッと自分をみて気づく「価値」なのです。
「価値」に「普遍的」とついてますが、
それは、この世のすべてにある「価値」なんですよね。
これ以上、話すともう本文の内容がわかっちゃいますが、
その「価値」に気づいたら、「自分」というものが
本当にわからなくなっちゃんたんです。
「自分の意見をもちなさい」と世間はいいますが、
きっぱり、そんな「意見」はいらない。
僕が探しているのは、「哲学」。
全てに共通する「普遍的な考え」なのです。
そんなことを思ってたら、「自分」というものが
なくなっちゃたんです。
なぜなら、自分のなかにある「宇宙」に気づいたから、
「普遍的な価値」に気づいたから、
一つの石ころでも「まなざし」を向けられるようになったからです。
これは「悟り」ではありませんが「気づき」です。
一つの石ころに「まなざし」を向けられるように
なったら、もう「全て」と繋がっているのです。
そのとき、自分は、たった一つの石ころになっているはずです。
「普遍的な価値」というのは、僕にとって
そういうものだと思います。
そして、文祥さんは、そんなことを気づかせてくれた人です。
ぜひ、この本文を読んで、一つの石ころに「まなざし」を
向けてくれればな、と思います。

「大切にしてくれるもの」
僕の質問・疑問
文祥先生は、いつも、「死・生」とか、「孤独・愛情」とか、
「差別」のこととか、色々と話してくれますが、
文祥先生は、そういうことをいつも、考えているんですか?
文祥さんの答え
さいきん、色々と少年・少女の事件、けっこうあるよね。
あのことでも、いろいろと考えていたのだけれど、
不思議だと思わなかった?
僕の質問・疑問
不思議というか、怖いですよね。
文祥さんの答え
なるほどねぇ。 でも私は、ちょっと違うことを考えていてね。
あういう子どもたちは、悪いのだけど、
あういうことは、起こりうるだろうな、と考えているんです。
そして、そこから、いろいろと考えたのだけれど、
不思議だなぁと思うのはね、
人間、生まれてくるとき、「生まれる?生まれない?」と
聞かれないでしょう?
聞かれた覚えもないでしょう?
僕の質問・疑問
ないです。
文祥さんの答え
私も、そうなんだよね。
気が付くと生まれているわけじゃないですか。
そうすると、やっぱり、自分は
どこから来て、どこへ行って、自分がなんだ?って
わからないんですよね。
それで、私もね、「津南町の山奥のお寺で生まれてくる」って、
聞かれれば、「やだ!!」とか言うんだよね。
でも、例えば「いいよ」と言って生まれてくれば、
雪が多いとか、山奥だとか、貧乏だとか、お寺だとか、
全部、引き受けられますよね。
だから「お前、お寺になるんだよ」と聞いてね、
「わかった、お寺になる」と言って生まれるのはいいのだけれど、
生まれてきちゃって、「お前、お寺やるんだよ」と
言われると、嫌なんだよね。だから、納得しないわけ。
目的なく、ポッと生まれてくるから、
ダメなんだよね。
何やっていいか、わからない。
さっきみたいに、極端なこともおこりうるんだよね。
僕の質問・疑問
極端なことというのは?
文祥さんの答え
殺人とかさ・・・
僕の質問・疑問
それは、どういう意味?
文祥さんの答え
だから、始めから何やってもいいし、
何もやらなくてもいいという形で、
ポッと生まれてきてるわけ。
それで、「あなた、人殺ししてはいけませんよ」とか、
「良い子でいなければいけませんよ」って
納得して生まれてくるわけじゃないから、
何、やってもいいという状態でうまれてくるわけですよ。
それが、お母さんが「これやっちゃいけない」とか
言って、だんだん、こうなってくるのだけど、
バッと置かれると、何をしていいかわからない。
なんでも、やってもいいとなるわけ。
そして、それと同様にポッと生まれてくるから
人間は「一人」なんだよね。
「お寺の子、やだな」と思って、話すじゃないですか、
でも、だれもわかってくれないんだよね。
そういうものなんですよ。
どんなに、仲のいい友達同士で、
「話し、わかっているな〜」と思っていても、
やっぱり、分からないところがあるんだよ。
だから、「一人」なんですよ。
そして、何が一番、切ないかというと、
「一人」なのが、一番、切ない。
なんとなくわかる?
僕の質問・疑問
なんとなくわかります。
文祥さんの答え
つまり、不安で、歩かれないんですよね。
あ〜、この世の中は、自分、「一人」だけだな。
誰もわかっていないな、と思うんです。
それが切ない。
それで、一番、そういう気持ちをわかってほしいのは、
「お母さん」なんだよね。
お母さんは、子どもを大事にしないと、
「認め」ないと、
子どもは、おかしくなりますよ。
僕の質問・疑問
つまり、100%、話しがわかる人はいないけれど、
「認めようと」してくれる人と、いないとでは
違うってことですか?
文祥さんの答え
そうです。
僕の質問・疑問
それで、やっぱり、お母さんやお父さんのほうが、
そういう力は、あるということですよね?
文祥さんの答え
そうです。そうです。
母親が、私に「お前、大事だ」って、
私のことをね、大切だっていうと、私は、歩けるんですよ。
だから、そういうふうなことが、まったくないと、
子どもは、死にたくなる。 生きていけないんですよ。
例えば、倫太郎君であれば、「倫太郎、大事だ」って
言ってくれる人がいたら、大丈夫なんですよね。
それが「愛」、もしくは「慈悲」ということなんです。
(仏教では、「愛」は自己愛、欲の意味で使われますので、
ここでは、すべての人に注がれる「慈悲」という言葉をつかいます)
つまり、「慈悲」は、必要だってことだから。
そして、「お母さんは必要だ」って言う人がいないと、
歩けない。
だから、生まれてきて、「一人」で、
どうやっていいか、わからないときに
「私は、あたなが大切だ」って、
しっかり、あなたのことを大事に思っている、と
言ってくれなきゃだめですよ。
何回も言いますが、それが「慈悲」なんです。
そして、先に行ける勇気を与えてくれるというわけ。
そうやって、繋がっているわけですよね。
でもね、これ、問題もあってね、今度、お母さんもあるわけだよ。
お母さんは、お母さんでもって、一生懸命やって、
生きがいになっているわけだけれど、
ふと、「自分て一人じゃないかな」と思うことがあるんだよ。
そういうときに、誰かが、例えばお父さんが
「お母さん、大事だ」と言ってくれないと
お母さんも大変なんですよ。
僕の質問・疑問
さっき、お母さんに「お母さん、大事だ」と言うたとえで、
お父さんが出てきましたが、子どもでも、
誰でもいいんですよね?
文祥さんの答え
子どもでも、いいんです。
僕の質問・疑問
喋れないですけど、動物とかでもいい?
文祥さんの答え
いいです。
僕の質問・疑問
海とかでも、山とかでも、そういうものでもいい?
文祥さんの答え
もちろん、そうです。必ずわかるから。
例えば、倫太郎君がお母さんに
「ぼくにとって大事だ」と言ったときにね、
お母さんは「あ、一人じゃないんだ」とこう思うわけですよ。
それは、倫太郎君の「慈悲」なんだよね。
これは、必ずそうなんだから。
それで、私だって、「あなた、いらない」とかさ、
言われると、「やっぱ、そうなのかな」と思ったり
するんですよね。
それで、犯罪がおきる。
だから、このことは、大事なことなんですよ。
どうだったかは、わからないけれど、
さいきんの少年・少女の事件は「お前、大事だ」って
言ってくれる誰かが、いるか、いないかっていうのは、
すごく、大きかったと思っています。
もしかしたら、ちっちゃいときから、そうだったかもしれない。
僕の質問・疑問
でも、何で、殺人とか犯罪とかをやるんですかね・・・
文祥さんの答え
だから、ちっちゃいころから、そうやって、
大事にされないと、慈悲が、わからないわけですよ。
自分が、大事にされてないと、人も大事にしないから。
私、「慈悲」って言うじゃないですか。
あれは、ポッと理由もなく生まれてきて、
どうやっていいかわからない人に
「生きていけるんだよ」という力を与えてくれる。
僕の質問・疑問
その力となるのが、仏教でもいいわけですよね?
文祥さんの答え
もちろん、仏教でもいいんです。
でも、これが、ないと切ないんだよね。
まぁ、ともかく、これまで、言ってきた通り、
この事件は、考えさせられましたよね。
僕の質問・疑問
でも、そこをみんなは、見ていないんじゃないですか?
「心の教育が足りなかったから」とか
「精神的に異常があったから」とかに決めつけていると思います。
だから、考えてないんですよね。
文祥さんの答え
そうそうそう。
決めつけると、そこから、進まないもんね。
どこでも、答えをみつけて、そこで安心してしまうとね、
なにも本質が見えなくなっちゃうんだよね。
僕の質問・疑問
答えがあると、逆に何も起こらないということですよね。
文祥さんの答え
そうです。
僕の質問・疑問
死とは何か?とか、そういうのも考えるじゃないですか。
そういうのは、「答え」が重要なのではなく
なんというか・・・
文祥さんの答え
「問い続ける」ってこと?
僕の質問・疑問
そうです!そうです!
その言葉、いいですねぇ。
文祥さんの答え
録音機にちゃんと「問い続ける」の言葉、入った?(笑)

「生死についての哲学」
僕の質問・疑問
それで、「問い続ける」のことで、思い出したのですが、
「自然の境界線はどこにあるのか?」ということを
思っていて、それで考えて思いついたのが、
「問う」ことが「答え」なのかな、と思っていて、
文祥さんの答え
それで、いいと思いますよ。
それで実は結論を見つけることがいいんだろうけど、
そこに価値があるわけじゃなくて、
ず〜っと、問い続けることに意味、「価値」があるんですよね。
私もそうですよ。例えば、20歳のとき、
わかったつもりでいても、
30歳のとき、突然、わからなくなってくる。
そして、40歳になると、もっとわからなくなっちゃうんですよね。
そして、そして、50歳になったりするとね、
「どうなのかな?」と考えはじめたりする。
だから、年によっても変わるんですよね。
それで、いいんです。
僕の質問・疑問
文祥先生は、今どんなことを考えているんですか?
文祥さんの答え
私は、やっぱり「生死(しょうじ)」とかそういうことを
考えますよね。
それで、私、お葬式するでしょう、
そのとき、また一層、意識するよね。
このあいだもね、お葬式に行ってきたんだけど、
58歳くらいの人が亡くなったわけ。
そういうことは、お父さんもお母さんも、
いるわけですよね。
そのお父さんの嘆き、哀しみていうのが、
大変で、やっぱり考えちゃいますよね。
そして、こうゆう時に、やっぱり悲しみはないほうがいい、
と思っちゃいます・・・
うん。
だから、いつも、そういうことを感じていますよね。
僕の質問・疑問
「死」とかが身近だということですよね。
文祥さんの答え
親しんできたしね。(笑)
でも、本当にそうだと思います。
「親和的」という言葉があるのだけど、
親しく思う、という意味なんだよね。
「死」というのは、
「縁起でもない」とかいって、
みんな、嫌がるじゃないですか。
でも、私は、「死」ということについて、
「親和的」だと思っていますね。
そんなにイヤなもんじゃないんじゃないかな、とかね、
良いんじゃないかとか、そんな気持ちをもっています。
僕の質問・疑問
何で、そういう気持ちになったんですか?
文祥さんの答え
ここ(お寺)に生まれたからじゃないかな。
そして、家にずっと居るばあちゃんが、
「死にたい、死にたい」と言うし、
「死」が身近だったんですよ。
それで、イヤなものじゃないという気持ちがあって
死っていうものは「良いもんだなぁ」と思っていたんです。
さっきのばあちゃんと親しかったからだね。
僕の質問・疑問
ばあちゃんが「死にたい、死にたい」と言っていたから、
「良いもんなんだなぁ」と思っていたわけですね。
文祥さんの答え
あのね、年をとったばあちゃんていうのは、
世の中がイヤになったりするんだよね。
それで、もう仕事をやったし、
もうイヤだなぁ、と思う気持ちがあるんですよ。
そうすると、必ず「死にたい、死にたい」と
言うんですよね。(笑)
そうすると、孫は「よっぽどいいものだ」と思うんです。
だから、ちっちゃいときから、
「死」がすぐそばにあったね。
僕の質問・疑問
そうですよね。
そして、昔って、家で葬式をするじゃないですか、
それで、結構、お酒を飲んで、楽しそうなんですよね。(笑)
だから、やっぱり「死はいいものだ」と思っちゃいます。(笑)
文祥さんの答え
昔の邪馬台国でも、そうだったみたいですよ。
悲しんでいるのは、ごくごく身内だけで、
あとは、まわりは、お酒を飲んでる。
騒いでる。(笑)
僕の質問・疑問
なるほど
そして、さっきのおばあちゃんのことについて、
もう少し、きいてもいいですか?(笑)
おばあちゃんは、「死にたい、死にたい」と
ひとりごとのように言っていたんでしょうかね?
文祥さんの答え
ひとりごとのようにも言ってもいたし、
私の顔を見ると、「死にたい」と言うんだよね。(笑)
そして、眠っている姿を見ると、
死んでるみたいだしさ・・・・
それで、そっと触ってみて「あ、生きてるな」と。(笑)
僕の質問・疑問
おいくつまで、生きられたんですか?
文祥さんの答え
72歳くらいかな。
とても、可愛がってくれたんですよ。
僕の質問・疑問
文祥せんせいは、おばあちゃんの死にゆくさまっていうのを
ずっと見ていたんですか?
文祥さんの答え
見てましたよ。
僕の質問・疑問
亡くなるところも?
文祥さんの答え
家だから、見てました。
静かに亡くなって行ったけどね、
「あぁ、なるほどな」と良いもんだなと。(爆笑)
いや、ホントですよ。
でも、今は、家で亡くならないで、病院で亡くなるからね。
僕の質問・疑問
それだし、今、核家族ですもんね。
でも、実際、面倒なこともあるじゃないですか。
ご飯が固いだの、柔らかいだの・・・(笑)
今日は、じいちゃんとそのことで揉めてきて、
ここに来たんですけど、老人になると、
柔らかいもの=美味しい、となるんだとか、
「老いる」っていうことがわかるんですよね。
一緒に住んでいると、そのさまが見えてくる。
でも、たまに来るだけじゃ、わかるはずがない。
だから、一緒に住んでないと
「老い」を知らないから
「老い」が嫌で、びっくりするんですよね。
だから、「老い」を逃れようとして、
「若返り」というのが流行っている。
一緒に居て、「老い」を感じていれば、
そんなに怖いことでもないし、
そういうことは大丈夫だと思うんですけど・・・
文祥さんの答え
それが、自然なことだと思うね。
僕の質問・疑問
そういうことを感じていないから、
「老いる」ことが怖いんでしょうかね?
文祥さんの答え
そうだと思います。
「老いる」ことは、「価値」がないことだと、
マイナスだと、思っているんでしょうね。
でも、「老いる」ことはマイナスじゃない。
わかならいことが、わかるようになったりするんですよね。
僕の質問・疑問
それで、思い出したんですけど、
あの松尾芭蕉が、30歳で「翁」と呼ばれたんですよね。
それは、おじいさんみたいに、熟練というか、
考え抜いたから「翁」なんですよね。
だから、むかしの人にとって、「翁」とは
嬉しいというか、良い言葉なんですよね。
文祥さんの答え
そう。良いことなんだよね。
それで、昔の掛け軸とかあるでしょ、
あそこに出てくるのみんな、老人ですよね。
こんな人(腰を曲げる動作)ばっかり、出てくるじゃない(笑)
でも、あれは、からかっているわけじゃないんですよね。
あれが一つの「理想」なんだよ。
人間の「理想」が、「老人」なんです。
だから、老人というのは、マイナスじゃなかった。
みんなが「あぁいいね」と、言っていたんですよ。
僕の質問・疑問
だから、やっぱり今の人たちは怖いのかなと思って。
これも「老い」の怖さと似ているんだけど、
会社とかそういうところに勤めていて、
それで「○○会社の△△さん」とか、
あるじゃないですか。
でも、定年して、その呼び名がなくなると、
呼び名が自分の名前だけになるんですよね。
そういうのが「怖い」でしょうね。
そして、「老いる」のも怖い。
でも、「会社」というのは、あるようでないものですよね。
「学校」もそう。あるようで、ないんですよ。
「作りごと」なんです。
まぁ、一緒に集まるのは、都合がいいのだけれど、
別に・・・
文祥さんの答え
そうなんですよ。別にたいしたことないんです。
だから、自分が「ほんとうの自分」なのか、
わからなくなるんだよね。
会社に居る時は、いいんだよ、
「△△銀行の○○です」と言っていればいいんだもん。
でも、それがなくなったときにどうするか。
僕の質問・疑問
どうしますか?
文祥さんの答え
そのときに初めて「ほんとうの自分」が出てくる、
ということですよね。
だから、それまで、ちゃんと「問うて」なきゃだめですよ。
それで、パッと亡くなったときに
「自分は誰なんだ?」みたいな話になるんです。
だから、ややこしいんだよね。
ところが、これは問い続けなければいけなくて、
問い続けるんだけど、結局、わからないところがある。
「自分が自分で何者であるか」というところに
到達するのは、大変なことなんですよ。
でも、一番、手っ取り早いのは、
「死者」に証明してもらうのが手っ取りばやい。
僕の質問・疑問
「死者」は喋られないんじゃないんですか?
文祥さんの答え
いや、そういうことではなくて、
自分は「ここの集落のだれだれの子ども」だって、
先祖をさかのぼっていくんです。
僕の質問・疑問
先祖が、例えば、医者だったとかが、わかるということですよね。
文祥さんの答え
そうです。「俺の御先祖さまは名医だったんだぞ」とか言って、
それで「安心」するわけなんですよね。
つまり、どういうことかというと、
「自分」を「自分」で発見できないものだから
「他人」に証明してもらはないとだめなんです。
でも、だいたい死んだ人に証明したがってますよね。
江戸時代にさかのぼって、「安心」したいんですよ。
でも、その前はわからない。
そんなことをやっていったら、
だいたいアフリカにいくんですよね。
僕の質問・疑問
え?そこまで行くんですか。
でも、そこまでいって、調査を頼んだひとは、満足するんですかね?
文祥さんの答え
最終的には、アフリカの1人の女性になるわけだけど、
そこから先は、どうするか?っていうふうになるわけですよ。
僕の質問・疑問
その先は、どうなるんですか?
文祥さんの答え
「宇宙」ですよ。
僕の質問・疑問
アフリカで終わった、と思いきや「宇宙」がある。
ていうことは、自分のなかにも「宇宙」があるから、
「宇宙」に行かなくても・・・・
文祥さんの答え
見つけられればいい、ということですよね。
僕の質問・疑問
自分のなかにみんなあるっていうことですか?
文祥さんの答え
だから、倫太郎君と「宇宙」はつながっているというわけですよ。
「一つ」っていうこと。
それが分からないから、自分と宇宙とは、関係ないと思っている。
でも、そうではないんです。
僕の質問・疑問
どんなこと、もの、でも関係あるということ?
文祥さんの答え
そうですね。
そうやって、気づくと、色んなものがないと自分は
生きていかれない、ということに気づいていく。
僕の質問・疑問
みんなに意味がある?
文祥さんの答え
そう。
僕の質問・疑問
石ころでも?一つの砂でも?
文祥さんの答え
あります。絶対にある。
それで、それを同じ、重さだと思ってなかきゃダメだね。
例えば、ペンには意味があるけれど、録音機には意味がないとか、
そういうものじゃなくて、それぞれが同等の「意味」を
もっている。人間もみんなそうだと思います。
「善い悪いって何?」
僕の質問・疑問
ちょっと、話しが元に戻りますが、
さいきんの少年・少女の事件の話しがあったじゃないですか。
そのことで、「善い・悪い」ってなんなんだろう?と
思っているんですけど、「善い・悪い」ってどういうふうに
考えるものなんですか?
文祥さんの答え
まず、「善い・悪い」というのは、大問題ですよね。
それで、だいたい世の中は、
「法律」とか、ああいうものに照らし合わせているんだけど、
たぶん、「善い・悪い」の基準、それは、
倫太郎君の人生が充実した方向にかなっていれば、いんだよ。
僕の質問・疑問
でも、もし大嫌いなひとがいて、その人を殺したら、
充実=善いことになるんですか?
文祥さんの答え
いや、それは、絶対に「むなしい」ことだから
僕の質問・疑問
上っ面では、喜んでいるように見えるけど、
「本心」では「むなしい」ということですよね。
だから、「ほんとう」の充実した人生、
「ほんとう」なんですよね。
文祥さんの答え
そういう方向に向かう、判断をすると、
「正しい」ことを・・・
僕の質問・疑問
それってどういうふうに判断できるんですか?
文祥さんの答え
こんなことをやろうと思うのだけど、自分の体を壊すな、とか
人を傷つけた、それが結果してね、自分の不幸になるなとか
そういうことですね。
だから、倫太郎君が幸せになるには、絶対にまわりの人を
幸せにしないと、ダメというわけです。
「ひとり」では、幸せになれないから。
僕の質問・疑問
ぜったいに?
文祥さんの答え
なりません。 美味しいものを食べるとか、そういうのではなくて、
心がやすらぐ時というのは、まわりの人がそうじゃないと、
絶対にならないんだよね。
また、倫太郎君も、心豊かでないと、
辛い人のことはわからないから。
僕の質問・疑問
ちょっと、話しが戻りますが、
「充実した人生」とはどんなものですか?
文祥さんの答え
まず、どうしようもないんだけど、
生きているとね、心のなかに、
穴が空いたような日々ってあるんですよ。
何やっても、「ほんとう」じゃないな、とか
そういうのって最悪だと思うんだよね。
それで、穴を埋められると、良いと思うんです。
全部、埋まるかどうかは、別にしてなるべく埋めていく。
僕の質問・疑問
それはどういうもので、埋まるんですか?
文祥さんの答え
それは、なかなか、わからないね。
不幸感という感じで持っているから、
おそらく、芸術とか、思想とか、音楽とか、
哲学とか、文学とか、宗教とか、そういうもので、
埋めようとするんだよね。
でも、その「埋めよう」という気持ちが、
文学とか、思想とかというものを作り上げていくと思うんです。
僕の質問・疑問
だから、「むなしい」ということが
思想とか、芸術を生む、というわけなんですね。
文祥さんの答え
そうです。動力の「原点」だと思いますね。
だから、「100%」幸福な人から、生まれてこないと思う。
「100」で、満たされているから、なにもないんだよね。
僕の質問・疑問
じゃあ、ブッタはどうなんですか?
文祥さんの答え
ブッタも最初、そうだったと思いますね。
僕の質問・疑問
だから、伝えることができたんですね。
文祥さんの答え
そうです。
それで、最後、ああいう形(涅槃)に、なったわけだよね。
でも、あの人(ブッタ)は、特別だよ。
普通の人が、あの「境地」をすぐに求められるかっていうと
なかなか、なれないと思うんですよね。
結局、あの人は、埋まったんだと思う。
その状態で、みんなに伝えようとしたんです。
僕の質問・疑問
じゃあ、ほんとうに別の感じですよね。
それで、人間の方に戻りますが(笑)、
人間は、「むなしさ」がないと芸術とかが、
生まれないということですね。
文祥さんの答え
わたしは、そう思うね。
僕の質問・疑問
マイナスのことというか、犯罪とかもですか?
文祥さんの答え
犯罪もそうだと思う。
僕の質問・疑問
じゃあ、芸術も「むなしさ」から生まれてくるし、
マイナスの犯罪も「むなしさ」から生まれてくる。
そういうわけですね。
文祥さんの答え
ただ、面倒なことがあってね、殺すことを
楽しく感じる人がいるんですよね。
「むなしさ」を超えてしまった人。
僕の質問・疑問
でも、昔の人から聞いた話ですけど、
昔は、カエルとかを殺していた男の子もいたって聞きました。
それとこれとは、同じですか?
文祥さんの答え
まず、子どもは、やっぱりそういうことをするんだよ。
それで、やり続けるんですよね。
でも、あるとき、「あ、いけない」と思うんです。
生きているのは、潰して殺すのはいけないんだという、
「気づき」があるんですよ。
僕の質問・疑問
それはどういうふうに?
文祥さんの答え
よく、わからないのだけど、
「かわそうなことをしたな」と思う瞬間があるんだよね。
私もそうでした。
鳥かなんかを銃で撃ったことがあるんだよ。
僕の質問・疑問
え?
文祥さんの答え
当たらないと思ったら、当たっちゃたんだよね。
昔は、エアガンというのが結構あって、
エアガンで撃ってしまったんです。
スズメみたいな小さな鳥だったんだけど、
下から狙って撃ったんですね。
そんなの当たらないのに、その日に限って、
当たっちゃったんだよね。
さっきまで、「ピーピー」と鳴いていた鳥が
撃ったら、くるくるくると回って、下に落ちてきてしまったんです。
それで、その落ちてきた鳥を見るじゃないですか、
そしたら、目をつぶって普通の鳥になっていたんですよね。
そのとき、この鳥を自分に殺す権利なんてあるわけが
ないというふうに思いましたね。
そして、ものすごく悪いことをしたと感じたんです。
それから、エアガンで撃つのはやめましたね。
僕の質問・疑問
ということは、何かに「気づく」ときがある、ということですね。
文祥さんの答え
そう。「気づく」ときがあるんだよね。
成長する人には、そういうことがあるんだと思います。
僕の質問・疑問
それで、前、文祥先生と話したときに
「気づき」は大事だ、と話していましたけど、
色んなことに「気づく」?
文祥さんの答え
あるんですね。
僕の質問・疑問
どういうふうに?
文祥さんの答え
さっき言った、小鳥を撃ったとき、
「命をもてあそんではならない」と気が付くことがあるわけです。
僕は、友達をいじめたことがないので、
そういう感じはわからないけど、
おそらく、成長の中でそういうことに「気づく」人がいるんだと
思う。あるいは、「こういうことはやってはいけないんだ」と
教えられて「そうかな?」と思っていても、
「あぁ、やっぱりそうだな、ほんとうにそうなんだな」と
思うときがあるんですよ。
僕の質問・疑問
でも、だからといって、蛙を潰したり、鳥を撃ってしまったり、