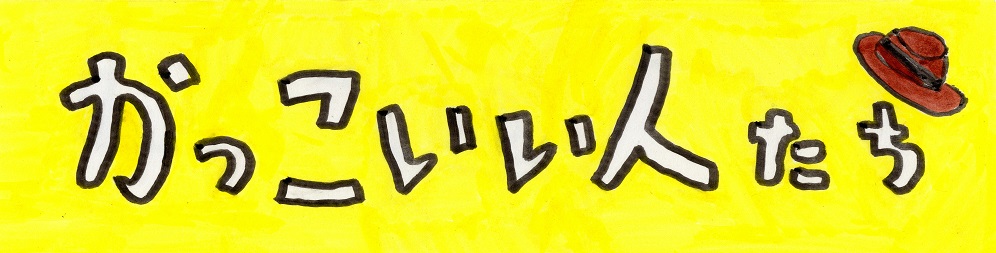
「かっこいい人たち」は、だれにでも「かっこいい」と思われる人じゃない。
ポレポレと話しを聞ける人。(ポレポレはスワヒリ語で「ゆっくり」)
自分の中に「見る」目をもっている人。
それが、その人の奥深くにある「かっこいい」ということ。
この「かっこいい人たち」では僕、別府倫太郎(通称ポレポレぼうや)が
「かっこいい人たち」を取材し僕の「目線」でお伝えします。
ポレポレと話しを聞ける人。(ポレポレはスワヒリ語で「ゆっくり」)
自分の中に「見る」目をもっている人。
それが、その人の奥深くにある「かっこいい」ということ。
この「かっこいい人たち」では僕、別府倫太郎(通称ポレポレぼうや)が
「かっこいい人たち」を取材し僕の「目線」でお伝えします。
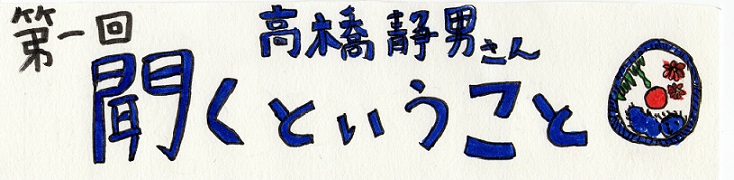

骨董屋「美宝堂」店主
高橋静男さんプロフィール
1947年(昭和22年)3月1日
新潟県津南町に生まれる
物理(素粒子)の先生として高校を主に36年間つとめる。
58歳で骨董屋「美宝堂」を津南町にて始める。
本人いわく、「骨董は素人だけど、モノは好きだし、
場所があったので始めてみた」という。
高橋さんとの出会い
「かっこいい人」と別府倫太郎が「なぜ」出会ったのか
高橋さんと僕とが初めて出会ったのは、「電波のこと」でした。
僕がなぜかは分からないのだけれど、「電波」というものに興味をもって、
そこで誰かこのことを知っている人がいないかなと、
思っていたら、僕の母が「高校の時、習っていた先生が「電波」とかに
詳しかったような・・・(僕の母は高校の時、高橋さんに習っていた)」と言い出したんです。
それで、その先生(高橋さん)のところに行ってみよう、というふうになって、
「美宝堂」に入ったら、僕の大好きな古いもののオンパレード。
その骨董に目を向けながら、「電波」のことを聞いたら、これまた、面白い話し。
僕の大好きなところでした。
それから、僕は「美宝堂」に通いつめ、現在に至っているのです。
今では、思想的なことや宇宙のことなど、色々な話しを聞かせてもらっています。
今、思えば、高橋さんの電波に僕のアンテナが反応したのかもしれませんね。(笑)
プロローグ「僕の落ち着くところ」
文章 別府倫太郎
骨董屋「美宝堂」。
骨董屋って言うと「大事」なモノが「大事」に飾られているイメージがあるが、
ここは少し違う。物と物とが共鳴していて少し不思議な、というか僕にとって落ち着く所。
それが美宝堂。この美宝堂の店主、高橋静男さんと僕は仲良くさせてもらっていて
高橋さんに会いによく美宝堂に行ったりしている。
その高橋さんをなぜ僕が「かっこいい人たちで取材する!」と決めたかというと
モノにでも人にでも何でも、話している・訴えている事を「聞ける」人だから。
それが、かっこいいと思う。
今、かっこいい人たちを読んでいる皆さんは「聞ける」という意味が
分からないかもしれないが、頭の中に置いておいて欲しい。
高橋さんの話を聞けば、だんだんと僕も皆さんも分かっていくと思う。
所で言うのを忘れていたが僕の中での「かっこいい」という意味は
イケメンとかではなく(笑)自然体、そこにいる事が「かっこいい」という意味。
それは生き方でもあるんだと思う。
そして「かっこいい人たち」に会うと目に見えないのだけれど、
オーラみたいなものを感じられる。
で、その「かっこいい人たち」・・・と考えていたら、
思いついたのが高橋さんだったのだ。
そして僕たち別府新聞は早速、高橋さんに会いに行くことにした。
車で行く事、20分。美宝堂に着く。
中に入ると骨董品がば〜っとあって、
まるで不思議な世界にいるみたいになる。
奥にはイスとシンク、ガスコンロがあって、おまけに蓄音機まである。
左には不動明王の像。右には江戸時代のお皿、アコーディオン。
見ているだけでワクワクする。
所で僕が美宝堂に行くのは骨董品を見たいからというのもあるが
僕が日々、思っている「疑問」を高橋さんに聞きたいから。
高橋さんに聞くと「答える」というよりも、
一つの疑問から「色んな世界」に連れて行ってくれる感じがする。
僕が思うにまるで「寺子屋」。
言っておくが学校とは全然ちがう。あくまで寺子屋なのだ。
そんな寺子屋「美宝堂」。
今回、僕が聞きたいのは高橋さんの骨董品でも人でもそれに対する「優しさ」。
もっと言えば先ほど言った「聞ける」ということ。
このことを高橋さんに聞いた。
そしたら、高橋さんは本当に色々な事を話してくれた。
この高橋さんの話をかっこいい人たちで少しでもお伝えできればと思う。
では高橋さんのお話し、始まります。

「聞くということ」
僕の質問・疑問
高橋さんを見ていると、ここにある骨董品にたいして「優しいな」と思います。
その優しさは高橋さんが、「モノを持つこと」の責任というか「モノと向かい合う」感覚が
あるからだと思います。そう教えられるものではないと思いますが、何でそんなに
優しくなれるのか、好きになれるのか聞かせて下さい。
高橋さんの答え
特別、僕がモノにたいして優しいということではないのだけれど、
人やモノが、世の中に「存在する」意味みたいなもの、
「どうして、そこにこんなモノがあるのかな?」と
こういうものをモノの場合はモノの「そのまま」を見て
それが何を訴えているか「聞こう」としている。
僕がモノに聞いていることは何かというと、それはおもに二つあります。
一つはモノそのものを、ずーっと使ってきた人のこと。
使ってきた人は「なんでこれを大事にしたのかな?」という心。
もう一つはそのものを作った人。
有名な人間国宝とか素晴らしい人が作ったモノは、誰もが知っているから
すぐ分かると思うんです。
所が僕の骨董品の99.9%は世の中に名が知られていない人。
だけど、その人は本当に一生懸命に、使う人のことを
考えてつくっているんじゃないかと思う。
だけど、多くの骨董品はそれを作っても、
ほんのわずかしかお金がもらえなかった。
一つ作っても二つ作っても三つ作っても。
だけど、そういう品物ほど見るたびに「いいなぁ」と思う。
でも、多くの人は「古い・きたない・使えない」と言ってすぐに捨てる。
本当にそうなのかともう一回、品物と向き合ってみる。
そうすると「これは何でできているんだろう?」「どうやって作っているんだろう?」と
色んな疑問が生まれるわけ。
その疑問に対して自分なりに答えていると
何となくモノと「お話」ができるんです。
話していて今、思いましたがモノと「話し」を
することは自分とモノを見ているけども、
実は話している相手はもう一人の自分なのかもしれません。
知らないうちに自分がモノに溶け込んじゃってそっちにも自分がいる。
そういうことかも知れません。
でも、僕がモノ全部と「話し」をするわけではないです。
例えば、ただ高価なモノというのは、
「う〜」とただ見ているだけで話しもしてくれないし、
こちらからもあんまり話しかけない。
すごく高価なモノだから「大事」に取り扱って、
それが欲しいという方には「大事」にお渡しする。
やっぱり一番、話をするのは人から見むきもされないもの。
これが僕の骨董品にたいする、ちょっと違うところかな。
僕の質問・疑問
なるほど。じゃあ、モノと話すことが好きというか楽しいということですか?
高橋さんの答え
楽しいかと言われると、むずかしいのだけれど
僕は楽しいというよりも、「聞こえちゃう」んだよね。
「これはダメだぁ」と言ってモノを捨てようとするじゃないですか。
すると何となく「もうちょっとよく見てから捨てなさい」というような
抗議の声が「ふっと」聞こえるんだよね。
そういうのは、できるだけ大事にする。
もちろん、聞こえないのもあるし、割れちゃって
「早く捨ててちょうだい」というのもある。
だから、僕がよくお客さんに言うんだけど、骨董屋に来たら無理して
「買っちゃいけないよ」と言うんだよね。
ただ、骨董品が「つれてって」と叫ぶときがあるから、
「今、つれて行かないと、この次いないよ」とそういう話をお客さんにする。
で、自分がやっぱりそうなの。
自分が「つれてきた」品物っていうのは「もうちょっと話しをつづけて」と
言っているものだから商品に出さないで「にやにや」しながら見てる。(笑)
ちょっと変かな?(笑)
ま、そういうことかなぁと僕は思っています。

「僕の解決できないこと」
僕の質問・疑問
じゃあ、先ほど高橋さんが言っていたように、
もう一人の自分と「話し」ているということは
自分のなかに「問い」がいつもあるから、「問い」が湧いてくるからですか?
高橋さんの答え
「問い」というよりも自分のなかで「解決できないもの」なんですよね。
例えば「きれいだ」というのはどういうところが、
きれいなのかと聞かれたら「こういうのがきれいだよ」と
示すことはできるけど、これとこれは「どっちがきれいだ?」と言ったら、
かならず人によって違うんだよね。
自分でもその時によって違う。例えばカレーを食ったあとは、
カレーはもう食べたくないと思うでしょう?
でも、人がカレーを食べていて自分が、おなか空いているとカレーを食べたいと思う。
そういうふうに一つのことにたいする、「こっちか・あっちか」というのが中々決めにくい。
そういうのをいつも僕は感じているんだよね。
例えば、「いいこと」か「悪いこと」かというのも非常にむずかしい。
あたまをカチーンと叩くのは、いいのか悪いのかといえば、
これはよくないというのがわかりますよね。
だけども、そのあたまをカチーンと叩かないかぎり眠っていて起きないとすれば
カチーンと叩かなければいけない。
その「行為」、これは同じであっても、「いい・悪い」というのは
やっぱり、むずかしいですよね。こういうのは昔からのテーマ。
そして僕の中にも「いいか・悪いか」
こういうのは常にず〜っとあるんです。
「そんなにいいことなのかな?」「そんな悪いことなのかな?」と。
そこでどうするかというと、まずは出来るだけそれについて「知る」ということ。
そうすれば、いいとか悪いとかじゃなくて自分でモノを見れる。
これ、骨董品でも同じなんだよね。
みんなが見向きをしなくても「惹きつけられる」。
これが先ほどのモノと「話す」という意味なんだよね。
このモノと僕とは波長が合うところがあるんじゃないかと。
そして色々と話してみると新しい発見があったり、
たんなる思いこみであったり・・・
で、その「新しい発見」があると面白いというか楽しい。
それが「あぁ〜やってて良かったな」と思う瞬間ですね。

「ただそれだけのこと」
僕の質問・疑問
高橋さんはモノにもそうですけど、人にたいしても、
すごく優しいなと思います。
僕が色んな事を質問すると、丁寧に話してくれてるなと思うんです。
そんな高橋さんが話すときや人と人のつながりの中で
大事にしていることがあったら聞かせて下さい。
高橋さんの答え
そうね・・・しいていえば「大事」にしないことかな。
「大事にする」ということは、相手の人の地位、職業、年齢などを
「ふまえて」話しているということ。
でも、僕の場合はそうじゃなくてお互いに「はだか」で
(はだかっていう言葉がいいのかわからないのだけれども)
というか自分のそのままをさらけ出して向こうもさらけだしてもらう。
お互いが、どんなに色々なことがわかっていても、色々なことがわかっていなくても、
上とか下はないんだろう、とそういうことですね。
だから、職業とか年齢とかは相手が話してこない限り「聞かない」。
「その人」と「自分」ということ「だけ」なんですね。
それは、人のことを無理に「追いかけない」ことでもあります。
そして、その追いかけないということには、もう一つ意味があるんです。
それは「人を無理に呼ばない」ということ。
来ていただくような「努力をしない」ということですね。
そのかわりに来た時間をひじょうに「大事」にする。
お互いにね。
うちに来る人たちは色々な人たちがいるんです。
その中には骨董屋なのに始めっから
骨董品なんかまったく見向きもしないで
一時間以上、骨董品じゃない話しを色々として
「じゃあね〜」と言って帰っちゃう人もいる。
この前、その人とお話しをしたのは「雪」についてだったのね。
その前は、山奥で一軒家に住むにはどうすればいいかとか・・・
とにかく、とんでもない発想が色々とあるのね。
だけども、その人がなんていう名前かも知らないし聞かない。
そんなふうに、それぞれ来る方々は色々なテーマをもっていたり
自分のなやみをもっていたりする。
その人が求めていることにたいして自分が、
きちっと対応できる保証はぜんぜん無いんだけどね。
だから、期待どおりに行かないかもしれません。
それでもよかったら来てくださいということですね。
だから、来る人はそれでもいいから美宝堂に来るんだと思う。
ただ、それだけのことです。

別府倫太郎の「締めくくり」
今回、高橋さんに色々と話していただきましたが、
一番、気になった言葉は「聞く」ということです。
他にも「モノと話しをする」というところは,
本当に「かっこいいな」と思いました。
そして高橋さんに話をうかがって思ったこと、
それは「聞く」ということや「モノと話しをする」ということは、
自然体じゃないと出来ないということ。
高橋さんが言っていた「自分をさらけだす」ということですね。
だから、高橋さんは僕にとって「骨董屋」という肩書きはなくて
やっぱり「高橋さん」というイメージしかないのです。
高橋さんは「怪しい骨董屋店主」と自ら言ってますけど。(笑)
まぁ、美宝堂はそんなにややこしく語らないほうがいいのかもしれません。
美宝堂は良くも悪くも「それだけ」つまり、「そのまま」なんですから。
僕は美宝堂のそういう「かっこよさ」にひかれているのです。

(かっこいい人たち「聞くということ」終わり)
作者
別府倫太郎 プロフィール

2002年12月5日生まれ。
新潟県十日町市在住。
3年前から始めた「別府新聞」の社長でもあり、
別府新聞のたった一人の社員でもある。
「学校に行っていない思想家」「ポレポレぼうや」など
色々な呼び名がある。
かっこいい人たち いままでのタイトル
「聞くということ」 2014-1-10更新
「大切にしてくれるもの」 2014-8-30更新
別府新聞ホームへ戻る
文章 別府倫太郎
骨董屋「美宝堂」。
骨董屋って言うと「大事」なモノが「大事」に飾られているイメージがあるが、
ここは少し違う。物と物とが共鳴していて少し不思議な、というか僕にとって落ち着く所。
それが美宝堂。この美宝堂の店主、高橋静男さんと僕は仲良くさせてもらっていて
高橋さんに会いによく美宝堂に行ったりしている。
その高橋さんをなぜ僕が「かっこいい人たちで取材する!」と決めたかというと
モノにでも人にでも何でも、話している・訴えている事を「聞ける」人だから。
それが、かっこいいと思う。
今、かっこいい人たちを読んでいる皆さんは「聞ける」という意味が
分からないかもしれないが、頭の中に置いておいて欲しい。
高橋さんの話を聞けば、だんだんと僕も皆さんも分かっていくと思う。
所で言うのを忘れていたが僕の中での「かっこいい」という意味は
イケメンとかではなく(笑)自然体、そこにいる事が「かっこいい」という意味。
それは生き方でもあるんだと思う。
そして「かっこいい人たち」に会うと目に見えないのだけれど、
オーラみたいなものを感じられる。
で、その「かっこいい人たち」・・・と考えていたら、
思いついたのが高橋さんだったのだ。
そして僕たち別府新聞は早速、高橋さんに会いに行くことにした。
車で行く事、20分。美宝堂に着く。
中に入ると骨董品がば〜っとあって、
まるで不思議な世界にいるみたいになる。
奥にはイスとシンク、ガスコンロがあって、おまけに蓄音機まである。
左には不動明王の像。右には江戸時代のお皿、アコーディオン。
見ているだけでワクワクする。
所で僕が美宝堂に行くのは骨董品を見たいからというのもあるが
僕が日々、思っている「疑問」を高橋さんに聞きたいから。
高橋さんに聞くと「答える」というよりも、
一つの疑問から「色んな世界」に連れて行ってくれる感じがする。
僕が思うにまるで「寺子屋」。
言っておくが学校とは全然ちがう。あくまで寺子屋なのだ。
そんな寺子屋「美宝堂」。
今回、僕が聞きたいのは高橋さんの骨董品でも人でもそれに対する「優しさ」。
もっと言えば先ほど言った「聞ける」ということ。
このことを高橋さんに聞いた。
そしたら、高橋さんは本当に色々な事を話してくれた。
この高橋さんの話をかっこいい人たちで少しでもお伝えできればと思う。
では高橋さんのお話し、始まります。

「聞くということ」
僕の質問・疑問
高橋さんを見ていると、ここにある骨董品にたいして「優しいな」と思います。
その優しさは高橋さんが、「モノを持つこと」の責任というか「モノと向かい合う」感覚が
あるからだと思います。そう教えられるものではないと思いますが、何でそんなに
優しくなれるのか、好きになれるのか聞かせて下さい。
高橋さんの答え
特別、僕がモノにたいして優しいということではないのだけれど、
人やモノが、世の中に「存在する」意味みたいなもの、
「どうして、そこにこんなモノがあるのかな?」と
こういうものをモノの場合はモノの「そのまま」を見て
それが何を訴えているか「聞こう」としている。
僕がモノに聞いていることは何かというと、それはおもに二つあります。
一つはモノそのものを、ずーっと使ってきた人のこと。
使ってきた人は「なんでこれを大事にしたのかな?」という心。
もう一つはそのものを作った人。
有名な人間国宝とか素晴らしい人が作ったモノは、誰もが知っているから
すぐ分かると思うんです。
所が僕の骨董品の99.9%は世の中に名が知られていない人。
だけど、その人は本当に一生懸命に、使う人のことを
考えてつくっているんじゃないかと思う。
だけど、多くの骨董品はそれを作っても、
ほんのわずかしかお金がもらえなかった。
一つ作っても二つ作っても三つ作っても。
だけど、そういう品物ほど見るたびに「いいなぁ」と思う。
でも、多くの人は「古い・きたない・使えない」と言ってすぐに捨てる。
本当にそうなのかともう一回、品物と向き合ってみる。
そうすると「これは何でできているんだろう?」「どうやって作っているんだろう?」と
色んな疑問が生まれるわけ。
その疑問に対して自分なりに答えていると
何となくモノと「お話」ができるんです。
話していて今、思いましたがモノと「話し」を
することは自分とモノを見ているけども、
実は話している相手はもう一人の自分なのかもしれません。
知らないうちに自分がモノに溶け込んじゃってそっちにも自分がいる。
そういうことかも知れません。
でも、僕がモノ全部と「話し」をするわけではないです。
例えば、ただ高価なモノというのは、
「う〜」とただ見ているだけで話しもしてくれないし、
こちらからもあんまり話しかけない。
すごく高価なモノだから「大事」に取り扱って、
それが欲しいという方には「大事」にお渡しする。
やっぱり一番、話をするのは人から見むきもされないもの。
これが僕の骨董品にたいする、ちょっと違うところかな。
僕の質問・疑問
なるほど。じゃあ、モノと話すことが好きというか楽しいということですか?
高橋さんの答え
楽しいかと言われると、むずかしいのだけれど
僕は楽しいというよりも、「聞こえちゃう」んだよね。
「これはダメだぁ」と言ってモノを捨てようとするじゃないですか。
すると何となく「もうちょっとよく見てから捨てなさい」というような
抗議の声が「ふっと」聞こえるんだよね。
そういうのは、できるだけ大事にする。
もちろん、聞こえないのもあるし、割れちゃって
「早く捨ててちょうだい」というのもある。
だから、僕がよくお客さんに言うんだけど、骨董屋に来たら無理して
「買っちゃいけないよ」と言うんだよね。
ただ、骨董品が「つれてって」と叫ぶときがあるから、
「今、つれて行かないと、この次いないよ」とそういう話をお客さんにする。
で、自分がやっぱりそうなの。
自分が「つれてきた」品物っていうのは「もうちょっと話しをつづけて」と
言っているものだから商品に出さないで「にやにや」しながら見てる。(笑)
ちょっと変かな?(笑)
ま、そういうことかなぁと僕は思っています。

「僕の解決できないこと」
僕の質問・疑問
じゃあ、先ほど高橋さんが言っていたように、
もう一人の自分と「話し」ているということは
自分のなかに「問い」がいつもあるから、「問い」が湧いてくるからですか?
高橋さんの答え
「問い」というよりも自分のなかで「解決できないもの」なんですよね。
例えば「きれいだ」というのはどういうところが、
きれいなのかと聞かれたら「こういうのがきれいだよ」と
示すことはできるけど、これとこれは「どっちがきれいだ?」と言ったら、
かならず人によって違うんだよね。
自分でもその時によって違う。例えばカレーを食ったあとは、
カレーはもう食べたくないと思うでしょう?
でも、人がカレーを食べていて自分が、おなか空いているとカレーを食べたいと思う。
そういうふうに一つのことにたいする、「こっちか・あっちか」というのが中々決めにくい。
そういうのをいつも僕は感じているんだよね。
例えば、「いいこと」か「悪いこと」かというのも非常にむずかしい。
あたまをカチーンと叩くのは、いいのか悪いのかといえば、
これはよくないというのがわかりますよね。
だけども、そのあたまをカチーンと叩かないかぎり眠っていて起きないとすれば
カチーンと叩かなければいけない。
その「行為」、これは同じであっても、「いい・悪い」というのは
やっぱり、むずかしいですよね。こういうのは昔からのテーマ。
そして僕の中にも「いいか・悪いか」
こういうのは常にず〜っとあるんです。
「そんなにいいことなのかな?」「そんな悪いことなのかな?」と。
そこでどうするかというと、まずは出来るだけそれについて「知る」ということ。
そうすれば、いいとか悪いとかじゃなくて自分でモノを見れる。
これ、骨董品でも同じなんだよね。
みんなが見向きをしなくても「惹きつけられる」。
これが先ほどのモノと「話す」という意味なんだよね。
このモノと僕とは波長が合うところがあるんじゃないかと。
そして色々と話してみると新しい発見があったり、
たんなる思いこみであったり・・・
で、その「新しい発見」があると面白いというか楽しい。
それが「あぁ〜やってて良かったな」と思う瞬間ですね。

「ただそれだけのこと」
僕の質問・疑問
高橋さんはモノにもそうですけど、人にたいしても、
すごく優しいなと思います。
僕が色んな事を質問すると、丁寧に話してくれてるなと思うんです。
そんな高橋さんが話すときや人と人のつながりの中で
大事にしていることがあったら聞かせて下さい。
高橋さんの答え
そうね・・・しいていえば「大事」にしないことかな。
「大事にする」ということは、相手の人の地位、職業、年齢などを
「ふまえて」話しているということ。
でも、僕の場合はそうじゃなくてお互いに「はだか」で
(はだかっていう言葉がいいのかわからないのだけれども)
というか自分のそのままをさらけ出して向こうもさらけだしてもらう。
お互いが、どんなに色々なことがわかっていても、色々なことがわかっていなくても、
上とか下はないんだろう、とそういうことですね。
だから、職業とか年齢とかは相手が話してこない限り「聞かない」。
「その人」と「自分」ということ「だけ」なんですね。
それは、人のことを無理に「追いかけない」ことでもあります。
そして、その追いかけないということには、もう一つ意味があるんです。
それは「人を無理に呼ばない」ということ。
来ていただくような「努力をしない」ということですね。
そのかわりに来た時間をひじょうに「大事」にする。
お互いにね。
うちに来る人たちは色々な人たちがいるんです。
その中には骨董屋なのに始めっから
骨董品なんかまったく見向きもしないで
一時間以上、骨董品じゃない話しを色々として
「じゃあね〜」と言って帰っちゃう人もいる。
この前、その人とお話しをしたのは「雪」についてだったのね。
その前は、山奥で一軒家に住むにはどうすればいいかとか・・・
とにかく、とんでもない発想が色々とあるのね。
だけども、その人がなんていう名前かも知らないし聞かない。
そんなふうに、それぞれ来る方々は色々なテーマをもっていたり
自分のなやみをもっていたりする。
その人が求めていることにたいして自分が、
きちっと対応できる保証はぜんぜん無いんだけどね。
だから、期待どおりに行かないかもしれません。
それでもよかったら来てくださいということですね。
だから、来る人はそれでもいいから美宝堂に来るんだと思う。
ただ、それだけのことです。

別府倫太郎の「締めくくり」
今回、高橋さんに色々と話していただきましたが、
一番、気になった言葉は「聞く」ということです。
他にも「モノと話しをする」というところは,
本当に「かっこいいな」と思いました。
そして高橋さんに話をうかがって思ったこと、
それは「聞く」ということや「モノと話しをする」ということは、
自然体じゃないと出来ないということ。
高橋さんが言っていた「自分をさらけだす」ということですね。
だから、高橋さんは僕にとって「骨董屋」という肩書きはなくて
やっぱり「高橋さん」というイメージしかないのです。
高橋さんは「怪しい骨董屋店主」と自ら言ってますけど。(笑)
まぁ、美宝堂はそんなにややこしく語らないほうがいいのかもしれません。
美宝堂は良くも悪くも「それだけ」つまり、「そのまま」なんですから。
僕は美宝堂のそういう「かっこよさ」にひかれているのです。

(かっこいい人たち「聞くということ」終わり)
作者
別府倫太郎 プロフィール

2002年12月5日生まれ。
新潟県十日町市在住。
3年前から始めた「別府新聞」の社長でもあり、
別府新聞のたった一人の社員でもある。
「学校に行っていない思想家」「ポレポレぼうや」など
色々な呼び名がある。
かっこいい人たち いままでのタイトル
「聞くということ」 2014-1-10更新
「大切にしてくれるもの」 2014-8-30更新
別府新聞ホームへ戻る